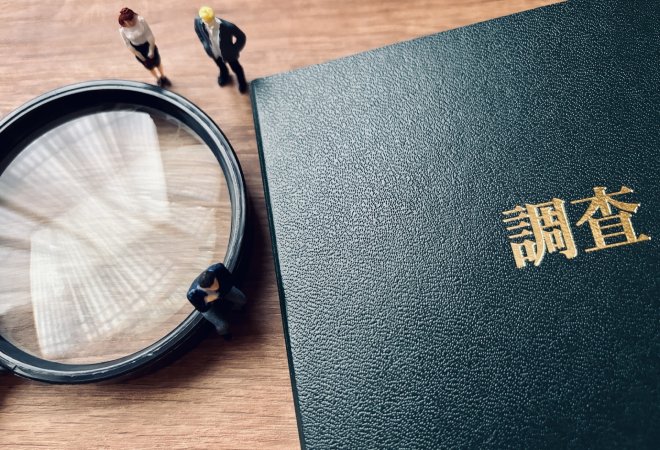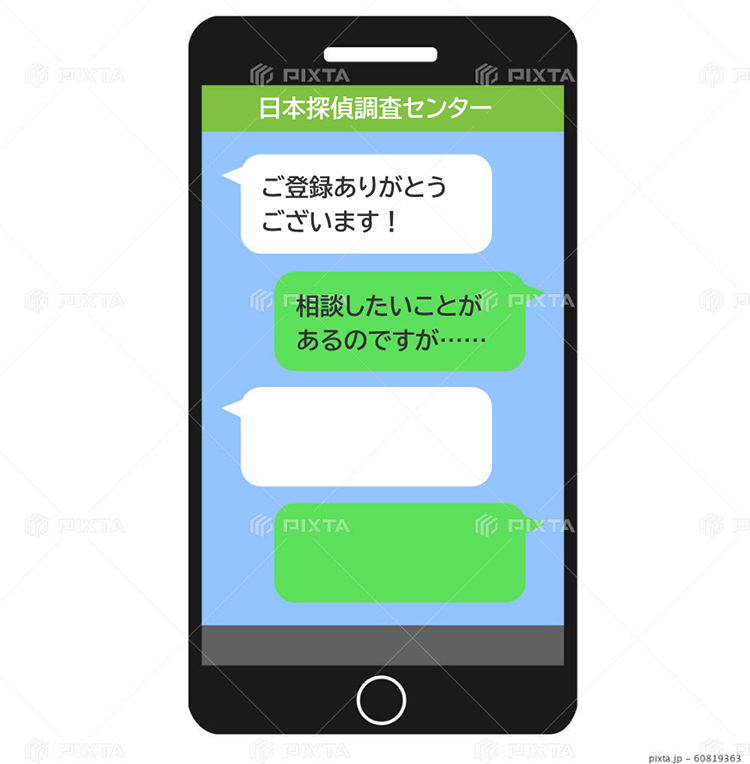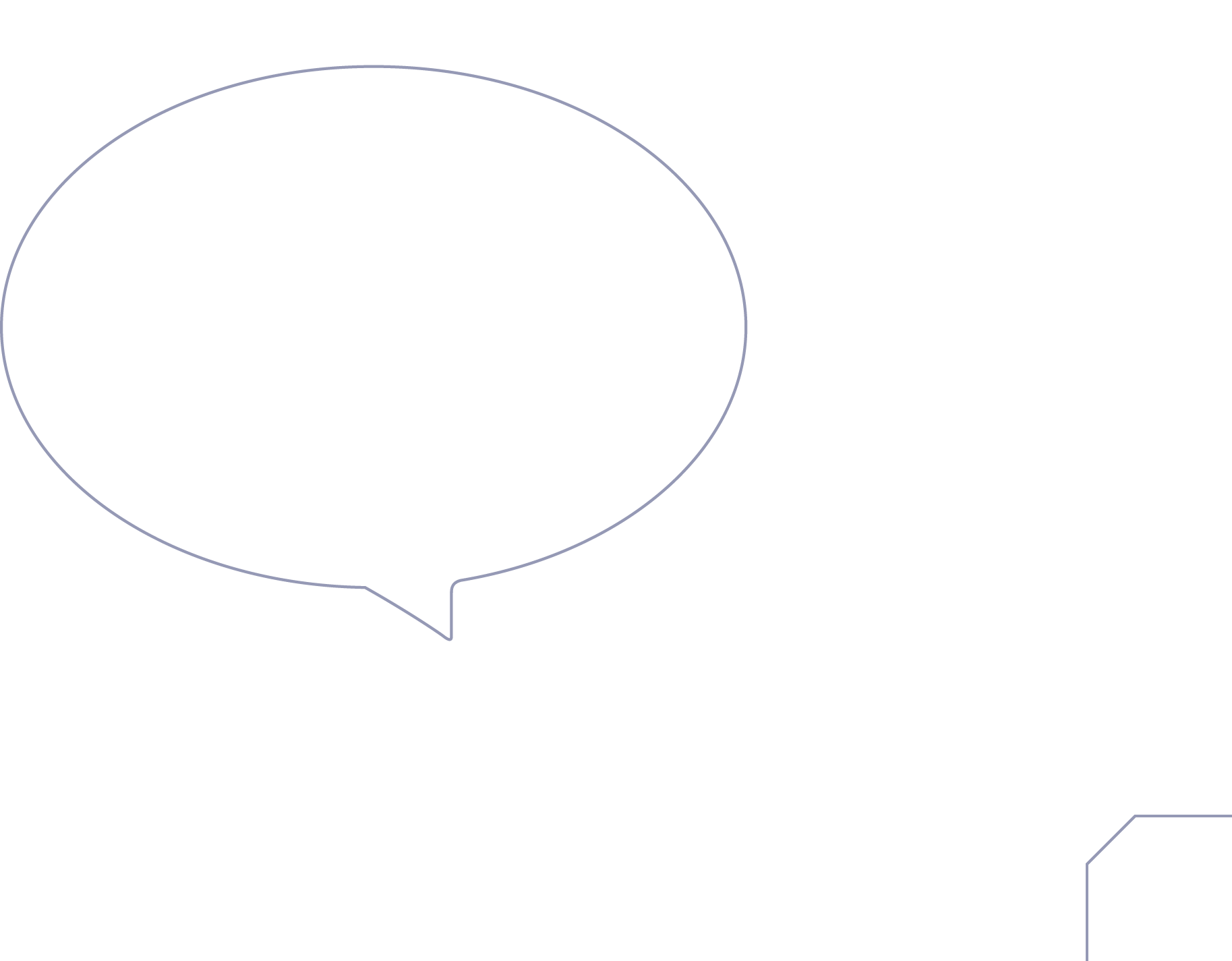子どもの症状、本当に五月病?不調の陰に隠れた深刻なSOS
更新日:2025-05-02
掲載日:2025-05-02

近年、子どもの間でも五月病が増加傾向にあります。しかし、その症状の裏には、いじめや性被害などの深刻な問題が隠れていることもあります。子どもは大人のように言葉で助けを求めることができず、『隠れたサイン』によって苦しさを伝えようとします。こうしたサインを見逃してしまえば、子どもをさらに追い詰めてしまう危険があります。本記事では、子どもの五月病に見える症状の背後に潜むリスクと、その異変の原因を明らかにするための具体的な方法について解説します。
目次:子どもの五月病の症状と隠されたSOS
- 子どもの五月病問題
- 子どもが隠しごとをしているサイン
- 子どもの変化に気づいたときに親ができること
- 子どものSOSを見逃さないために大切なこと
- 子どもの五月病に関する世間の声
- 子どもの異変を調べるには
- 迷ったときは専門家への相談を
子どもの五月病問題
五月病とは
五月病とは、新年度の環境変化によるストレスや疲労が蓄積し、心身に不調をきたす状態のことをいいます。大人に限らず、子どもにも起こることがあり、新しいクラスや人間関係に慣れないまま、心のバランスを崩してしまうケースがあります。放置すると、不登校や長期的なメンタル不調に発展するおそれもあります。
子どもに多い五月病の症状とは
子どもの五月病では、大人と同様に心身の不調が現れますが、そのサインはより曖昧で見逃されやすい傾向があります。よくある症状には「学校に行きたくない」「食欲がない」「眠れない」「頭が痛い」といった体調不良が続くことが挙げられます。さらに、無気力や集中力の低下、情緒不安定など、性格が変わったように見えることもあります。こうした変化は一時的な疲れではなく、実は子どもからのSOSである可能性があります。
五月病の陰に隠れる子どもからのSOS
一見すると五月病のような子どもの不調の裏には、深刻ないじめや性被害が潜んでいる場合もあります。子どもは自分のつらさを言葉にすることが難しく、「学校に行きたくない」「体調が悪い」といった間接的なサインでしか伝えられないことがあります。これらを単なる気分の問題として片づけてしまうと、見えないSOSを見逃す結果につながりかねません。
子どもが隠しごとをしているサイン
子どもが抱える問題は、必ずしも言葉で表現されるとは限りません。むしろ「何も言わない」こと自体がサインである場合もあります。大人にとっては些細に思える言動の変化が、子どもからの必死のSOSかもしれません。ここでは、子どもが何かを隠しているときに見せる具体的なサインを紹介します。
突然、夜更かしや朝の寝坊が増えたり、食事の時間が乱れたりするようになった場合、それは子どもが心に不安を抱えているサインかもしれません。ストレスを感じていると、生活リズムの維持が難しくなり、親の目を避けるような行動を取ることもあります。特に、スマホに長時間没頭するような様子が見られるときは、心の変化が関係している可能性があります。
子どもが目を合わせなくなったり、会話の中に不自然な笑顔が見られたりした場合も、隠しごとのサインといえます。また、話しかけても反応が薄い、急に怒りっぽくなるなどの変化も要注意です。こうした微細な変化に気づくことが、子どもの異変を早期に発見するための重要な手がかりになります。
「お腹が痛い」「気持ちが悪い」と頻繁に訴えるものの、病院では異常が見つからない――こうしたケースでは、子どもが何かを隠している可能性があります。特に学校や特定の予定がある日に限って症状が現れる場合は、精神的な不安やトラブルを回避しようとしているサインかもしれません。身体の不調は心のメッセージとして捉えることが大切です。
子どもの変化に気づいたときに親ができること
子どもの異変に気づいたとき、親としてどう対応すべきか迷う方も多いはずです。感情的になったり、無理に聞き出したりすると、かえって心を閉ざしてしまうこともあります。大切なのは、寄り添いながら信頼関係を築いていくことです。以下に、家庭でできる実践的な対応法をご紹介します。
子どもの言動を否定せず、まず受け止める
子どもが不調を訴えたとき、「甘えないで」「もっと頑張れ」などと否定的な言葉をかけてしまうと、本音を話せなくなってしまいます。まずは「そうなんだね」「しんどいんだね」と受け止めることが大切です。安心感を与えることで、子どもは少しずつ心を開きます。正論よりも共感を意識することが、信頼関係を築く第一歩になります。
日常のちょっとした変化を記録しておく
子どもの変化に気づいたら、日記のように日々の様子を記録しておくことをおすすめします。「寝つきが悪い」「笑顔が減った」「スマホを手放さない」など、小さなサインの積み重ねが大きな手がかりになることもあります。また、学校や専門機関への相談時にも、記録は客観的な情報源として役立ちます。
学校との連携や相談機関を利用する
子どもの様子に不安を感じたときは、家庭内だけで抱え込まず、学校や地域の支援機関と連携することが大切です。担任の先生やスクールカウンセラーに相談することで、学校での子どもの様子を知ることができます。さらに、児童相談所や子ども家庭支援センターなど公的機関への相談も有効です。
子どものSOSを見逃さないために大切なこと
「いつもと違う」が続くときは見逃さない
子どもは言葉で助けを求めるのが難しいため、小さな行動の違和感が大きなサインになることもあります。たとえば、話しかけても反応しない、好きだったことに無関心になるなどの異変が生じているようであれば、何らかの異変を疑うべきです。気づいたときには優しく声をかけてあげましょう。

子どもに安心できる居場所をつくる
何かを抱えている子どもにとって、安心できる空間の存在は心の支えになります。「ここでは何を話しても大丈夫」と思えるような雰囲気を家庭内でつくることが重要です。話を聞くときはスマホやテレビを切り、子どもとしっかり向き合う時間を持つようにしましょう。大切なのは『正しい答え』ではなく、『受け入れてくれる存在』です。
無理に聞き出そうとせず、自然な会話を意識する
子どもが何かを隠していると感じたとき、問い詰めるような聞き方は逆効果です。緊張や恐怖で心を閉ざしてしまう恐れがあります。普段の会話の中でさりげなく様子をうかがい、リラックスした状態で本音が話せる雰囲気をつくることが大切です。目を合わせないで話せる場面、たとえば車内や散歩中などが有効なこともあります。
子どもの五月病に関する世間の声
甘えだと思っていたけど…|40代女性
不登校のきっかけでした|20代 元不登校経験者
無理矢理連れ出してしまった|40代男性
現在抱えている悩みや問題において探偵調査を利用したい、利用方法について知りたいという方は無料相談よりお問い合わせください。ご自身の抱える問題の解決法が分からない場合にもご利用いただけます。
子どもの異変を調べるには
原因を明らかにしましょう
子どもが不調を訴えるときには、必ずその背景に理由があります。「学校に行きたくない」「元気がない」といった表面的な訴えだけで判断するのではなく、何が本当の原因なのかを見極める必要があります。大人が冷静に状況を観察し、根拠に基づいた対応をすることで、適切なサポートへとつなげることができます。
探偵による調査サポート
いじめや性被害など、子どもが危険な状況に置かれている可能性がある場合には、外部の専門家による調査が有効です。探偵による調査では、周囲に知られずに行動確認や交友関係の実態把握が可能です。学校や家庭だけではつかめない情報が得られることで、早期の対応や安全確保、根本的な解決に向けた第一歩となります。
迷ったときは専門家への相談を
子どもの『本当の声』を見逃さないために
子どもの五月病と思われる不調の背後には、いじめや性被害といった深刻なリスクが潜んでいることもあります。子どもは不安や恐怖を言葉にできず、沈黙や態度の変化で訴えている場合があります。だからこそ、大人にはその『沈黙のサイン』を見逃さず、受け止める姿勢が求められます。不安な変化を感じたら、ひとりで抱え込まず、まずは専門家の無料相談を活用しましょう。
※本記事の相談内容は、探偵業法第十条に則り、実際の案件を基に一部内容を変更し、個人を特定できないよう配慮して記載しています。弊社では、個人情報保護法を遵守し、相談者および依頼人のプライバシーを厳格に保護することを最優先に取り組んでおります。